信時潔作曲作品のコンサート ― 2018/06/16 07:08
「信時潔旧蔵ピアノとリードオルガン修復記念レクチャーコンサート」では、 レクチャーの合間に、修復されたピアノとリードオルガンの演奏、そして歌唱 があった。 ピアノの井谷佳代さんとオルガンの中川紫音さんは横浜初等部教 員、メゾソプラノの穴澤ゆう子さんは横浜初等部非常勤講師、みなさん東京藝 術大学の器楽科、声楽科の卒業で、それぞれオランダやドイツの国家演奏家資 格を取得したり、文化庁芸術家在外研修員として留学したりした上で、活躍し ている方々だ。 横浜初等部(そして慶應義塾の一貫校)が優秀な教員を擁し ていることに、改めて感心する。
演奏されたのは、まずオルガンと歌で教会育ちの信時潔にちなんで、讃美歌 312番「いつくしみ深き」、文部省唱歌でアイルランド民謡・里見義作詩「庭の 千草」。 その後は信時潔作曲の作品で、文部省唱歌・生沼勝作詩「一番星見つ けた」・井上赳作詩「動物園」・佐野保太郎作詩「遠足」、ピアノ曲「木の葉集」 より、「序曲:楽想乱舞 口笛 わびしきジャズ 子守歌 おもいで 行進曲」、 歌曲集「沙羅」より清水重道作詩「丹沢」「沙羅」、北原白秋作詩「帰去来」、富 田正文作詩「慶應義塾塾歌」。
私は明治学院中学の毎朝の礼拝で讃美歌を歌っていたから、「いつくしみ深 き」は歌えるのだけれど、穴澤ゆう子さんの歌唱力にはのっけから圧倒された。 以下は、信時裕子さんのレクチャーによる。 ピアノ曲「木の葉集」は15曲、 昭和10(1935)年頃SPレコードになり、歌曲集「沙羅」も木下保の歌でレコ ードになったそうだ。
信時潔は昭和12(1937)年1月、「海ゆかば」を作曲した。 信時裕子さん は、『万葉集』の大伴家持作詩といわれているけれど、信時潔は「大伴氏言立(こ とだて)」という表記にこだわり、「言立」大伴家に代々伝わっているとしてい たという。 「海ゆかば」は、国民歌謡で歌われ、国民の歌に指定され、戦況 が悪化するとともに鎮魂歌のように使われるようになった。 以前、「海ゆかば」 と信時潔<小人閑居日記 2012. 12. 15.>に書いたように、信時潔は日本放送 協会から依頼されて、首相か大臣かの「おえら方」の放送の前に「聴取者の気 分を整えるために何か歌がほしい」とラジオ放送用の曲としてつくった曲が、 「本来の目的と違って、鎮魂歌として歌われたのは本人も不本意だったようで す。この歌は時代の空気にあったのでしょう」と、信時裕子さんは朝日新聞「う たの旅人」の牧村健一郎記者に語っていた。
昭和15(1940)年、管弦楽の伴奏がついた大規模な声楽曲(カンタータ)「海 道東征」を作曲して、評判となる(北原白秋作詩)。 演奏に1時間以上かか り、SPレコード8枚組(16面)、谷川俊太郎さんがこのレコードを持っている という。 現在も再演され、CDも出ていて、公演は100回を超す。
北原白秋作詩「帰去来」は、白秋が九州日々新聞文化賞を受け、故郷柳川に 帰った時の詩の絶筆。 柳川市が大事にしていて、毎年白秋祭で歌われる。
信時潔の作曲した校歌は900曲、社歌・団体歌は170曲。 校歌は日本にし かないので、世界で一番沢山校歌を作曲したのは、信時潔ということになる。 最近、各学校はホームページを開設しているので調べると、無くなった学校も あるけれど、900曲の内、半分以上が歌われている。 その中でも、最も完成 度の高いのが、「慶應義塾塾歌」で、昭和15(1940)年11月に印刷され、翌 昭和16年1月10日の福澤先生誕生記念会で初演された。 慶應には、明治 34(1901)年に創立されたワグネル・ソサィエティー男声合唱団があり、アカ ペラでも歌えるから、作曲者としては張り切ったのだろうと、信時裕子さんは 指摘した。
コンサートの最後に「慶應義塾塾歌」が、まず井谷佳代さんのピアノ、つづ いて中川紫音さんのオルガン、そしてピアノとオルガンの伴奏で穴澤ゆう子さ んの歌唱で演奏された。 ちょっと涙がこぼれそうになった。
信時潔の作曲した数々の美しい曲が、いろいろの機会に、もっともっと演奏 されればよいというメッセージを、高らかに響かせるコンサートとなった。
信時潔旧蔵のピアノとリードオルガン ― 2018/06/15 07:05
信時潔が作曲に使っていたこのピアノは、信時家の玄関を入ってすぐ、家の ほぼ中央の十畳ほどの畳の部屋にあって、奥につづく庭に出られるサンルーム 側に、ピアノとオルガンが置かれ、中央の壁際に大きな書き物机、一方の壁に は天井までガラス戸のついた造り付けの木の棚に大量の楽譜や本が仕舞われて いたという。 作曲中の写真には、譜面を鉛筆で書いていて、鍵盤の上に消し ゴムが写っている。 留学中、マルクの大暴落があって、大量の楽譜が買えた のだそうだ。
スタインウェイ社製のアップライトピアノで、昭和15(1940)年アメリカ で園芸(ツツジ、椿)で大成功した知人、清野主(つかさ)氏に贈られた中古 品だったという。 修復した太田垣至さんのレポートによると、Model-R(ハ ンブルグ工場製)か Model-I(ニユーヨーク製)と推測され、最も大きいタイ プの最上級機種で、豪華客船タイタニック号にも5台のスタインウェイ社製の ピアノがあったが、そのうち2台がModel-Rのアップライトで、ファーストク ラスで用いられていたという。 歴史的価値の高い、信時潔旧蔵のピアノの修 復には、できる限りオリジナルの部品の素材に近いものを厳選し使用した。 フ ェルト類は、楽器修復家G.ウォーカー氏による100%ピュアウール、皮革類は 皮鞣し職人P.ケンドルバッヒャー氏による鹿革を用いたそうだ。
オルガンを修復された伊藤信夫さんからは直接、解説を聴くことができた。 昭和8(1933)年神田生まれ、慶應義塾幼稚舎から、大学経済学部を卒業、東 京日産販売に入社したそうで、20年ほど前から奥様の弾くリードオルガンの不 調を直す内に、オルガンの修理・修復をするようになったという。 2017年の 信時潔旧蔵リードオルガンは68台目の修復で、その前年には慶應義塾日吉チ ャペルのリードオルガン(47台目)も修復、現在76台目に取り掛かっている。 信時家のリードオルガンは、YAMAHA製、ミイ夫人の大正12(1923)年の嫁 入り道具だったのだろう。 アメリカにベル・オルガンピアノ・カンパニーと いう会社があるが、第一次世界大戦(1914~1918)を境にして、ベル・ピアノ オルガン・カンパニーと改名した。 オルガンには、パイプオルガン、リード オルガン、電子オルガンの三種がある。 パイプオルガンと、リードオルガン は、悪くなったフェルト、皮、ゴム布を取り替えることで再生が可能、100年 でも、200年でも保つ。 電子オルガンは粗大ごみになる、そうだ。
横浜初等部で信時潔についてのレクチャーを聴く ― 2018/06/14 07:13
信時潔と、彼の作曲した「慶應義塾塾歌」については、2012年のこの日記に いろいろ書いていた。 改めて読んだら、信時潔の作曲した数々の作品や、信 時潔と福沢諭吉の生誕地が大阪の堂島川を挟んだ対岸にあることなどにも触れ ていた。
ベオグラードに響いた信時潔の「塾歌」<小人閑居日記 2012. 6. 18.>
「『塾歌』から見えてきた『信時潔』」<小人閑居日記 2012. 6. 19.>
「大学教授 与謝野寛―「幻の塾歌」の周辺―」<小人閑居日記 2012. 6. 20.>
西国分寺に響いた信時潔の「塾歌」<小人閑居日記 2012. 12. 14.>
「海ゆかば」と信時潔<小人閑居日記 2012. 12. 15.>
6月9日、慶應義塾横浜初等部で「信時潔旧蔵ピアノとリードオルガン修復 記念レクチャーコンサート」があり、青葉三田会のご縁で聴く機会を得た。 信 時潔の孫(次男の息子だそうだ)の信時茂さんが横浜初等部教員で、まず挨拶 をした。 『三田評論』2017年5月号「丘の上」に書かれた「祖父のピアノ」 によると、2017年2月に、国分寺市にある信時潔が関東大震災の翌大正13 (1924)年から亡くなるまで40年ほど住んだ築90年を超す家が取り壊され、 そこにあったピアノとリードオルガンが山内慶太前初等部長の勧めで初等部へ 寄贈、修復されることになったのだそうだ。 レクチャーと解説も孫の信時裕 子さん(三男の娘だそうだ)、長年祖父・信時潔を調査研究し、東京音楽大学(私 立)図書館司書、日本音楽学会会員、2009年に信時潔の自筆譜や蔵書、楽譜等 が東京藝術大学付属図書館に寄贈された際には、科研費助成事業「信時潔に関 する基礎研究」の研究員として同館・信時潔文庫の資料整理、目録作成を担当 したという。
レクチャーは、信時潔が明治20(1887)年、大阪北教会の牧師吉岡弘毅の 三男として生れ、高知教会(1歳~6歳)、京都室町教会(6歳~9歳)をへて、 大阪北教会に戻り、11歳で北教会の長老のひとり、信時義政の養子になったこ とから始まった。 教会に親しんだ幼時の生活が洋楽への道を拓き、オルガン と讃美歌とともに育つ。 大阪の市岡中学から、明治38(1905)年東京音楽 学校の入学試験は当時唱歌を歌うだけで、合格、チェロを専攻、チェロの先生 はいなくて本で勉強した(それで指の持ち方が違う)。 チェロの第一人者とい われた時期があって、大正13(1924)年のベートーベン第九の初演ではチェ ロのトップを務めている。 明治43(1910)年に研究科器楽部に進学、さら に作曲部で学んで大正4(1915)年修了(9年とちょっと学生だった)、助教授 に就任した。 大正9(1920)年ベルリンに留学、ゲオルク・シューマン(有 名なロベルト・シューマンとは別人)に師事、作曲(合唱曲「あかがり」はド イツで作曲。自筆譜が東京藝術大学付属図書館・信時潔文庫の貴重楽譜データ ベースで公開されているので、ネットで見られる)、合唱団指導などを学んだ。 帰国後、大正12(1923)年1月東京音楽学校甲種師範科卒で熊谷女学校教員 の白坂ミイと結婚、この年教授となる。 ミイ夫人は、作曲した楽譜の清書を し、秘書のような役割を果たした。 信時家のリードオルガンは、ミイ夫人が 弾いていたものらしい。 信時潔は、昭和6(1931)年東京音楽学校本科作曲 部の創設に尽力し、実現。 昭和7(1932)年、教授を辞任して講師となり(例 のないことで、事務仕事が苦手だったかららしい、以後作曲等に注力できた)、 定年まで週に一回は通った。 合唱、管弦楽団の指導、唱歌編纂にも関わる。 昭和7年、『新訂 尋常唱歌集』編纂の代表者となり、「秋の山」「一番星見つけ た」「公孫樹」「遠足」「影法師」「雁」「電車ごっこ」「動物園」「夏の月」「兵隊 さん」「ポプラ」「森の歌」「鷲」を作曲した。
熊谷守一、一時、慶應義塾に学ぶ ― 2018/05/30 06:42
25日の「等々力短信」第1107号「熊谷守一と信時潔」に、地方の素封家が 東京に家を持ち、子供達を学校に通わせているケースがあるが、「熊谷守一は、 どうだったろう」と書いた。 熊谷守一の父・孫六郎は製糸工場を営み、後に 初代岐阜市長となる。 熊谷の兄二人と熊谷自身も一時、慶應義塾で学んでい たという。 その答を求めて、福井淳子さんの『いのちへのまなざし―熊谷守 一評伝』(求龍堂)を読み始めた。
熊谷守一は、明治30(1897)年3月、岐阜尋常中学2年の過程を終えると、 10歳年長の長兄・銕太郎、7歳年長の次兄・鋭雄がそうであったように、東京 の学校に通うことになる。 長兄・銕太郎は、明治23(1890)年に慶應義塾 正科を卒業し、この頃には岐阜県恵那郡付知(つけち)村(現・中津川市付知 町)に戻って、地主の仕事、製材の仕事など、熊谷家の付知での仕事を担って いた。 次兄・鋭雄は、やはり慶應で学び、この頃は父・孫六郎が借りている 芝公園の家に住み、父が出資していた芝三田の東京硝子株式会社のガラス工場 の仕事を手伝っていた。 この家は、現在東京タワーの立つあたり、道を隔て て「紅葉館」という結婚披露宴も行われるような大きな料亭があった。 「紅 葉館」といえば、私などは、その前年の明治29(1896)年11月1日に、ここ で開かれた慶應義塾故老生懐旧会で、福沢諭吉が行った演説の最後に近い一節 が「慶應義塾の目的」という文書になっていることを思い出す。
熊谷守一は上京して、その次兄・鋭雄の芝公園の家に一緒に住み、同じ芝公 園の中にある正則尋常中学(現在の正則高等学校)に転入する。 ところがそ こで英語が劣っていることに気付き、築地にある英国人ジェイムズ・サマーズ の英語学校に通い、英語の勉強をしばらく続けるが、どうしても絵をやりたい という気持が日を追って強くなる。 上京してきた父に、思い切って「絵をや りたい、絵の学校へ行きたい」と相談する。 当然、絵では自活できない、と 父は絶対反対、守一は何度も説得を重ねる。 父はつい「もし慶應に一学期だ け通ったら、お前の好きなことをしてもいい」と言ってしまう。 兄ふたりが 慶應に通ったので、守一も慶應で学ぶうち、考えも変わるだろう、と思ったよ うだ。 守一は、父が「男が一度口にしたことは必ず守る」ことを身上とする ことを知っていた。 「しめた」と思い、「それぢや行きます」とすぐに寄宿舎 に入って、慶應で学び始める。 明治30(1897)年10月、慶應義塾普通科2 年3学期(9月始まり)への編入学だ。 守一は、和服に前掛けを締めて学内 を急ぎ足で行く福沢諭吉を何度か見かけたそうだ。 12月に3学期が終了、64 人のクラスで、守一は途中入学ながら、いい方の成績を残した。
井坂直幹と木都(もくと)能代 ― 2018/05/29 07:12
県北、能代市へ向かう。 井坂直幹(なおもと)の足跡を尋ねるためである。 井坂直幹という名だけは知っていた。 福沢は、明治13(1880)年12月、大 隈重信、伊藤博文、井上馨に政府の機関新聞発行の引受けを要請され、翌月政 府に国会開設の意があることを打明けられたので、協力を決意する。 その準 備に、中津出身の門下生(入社帳に記載なし)で水戸師範学校長だった松木直 巳に、優秀な若者の推薦を依頼する。 そして石河幹明、井坂直幹、高橋義雄、 渡辺治の4人が上京した。 4人は時事新報の記者となり、やがて石河幹明は 時事新報主筆・『福沢諭吉伝』の著者・『福沢全集』『続福沢全集』編者、高橋義 雄は三井各社役員・茶人箒庵、渡辺治は大阪毎日新聞社長となる。
そこで井坂直幹だが、主として編集局翻訳係の記者として4年間勤務の後、 明治20(1887)年3月26歳の時、時事新報社長中上川彦次郎の紹介で、文章 に長けた人を求めていた大倉喜八郎の秘書役となる。 大倉喜八郎は、深川の 大手木材問屋・九次米商店と提携し、林産商会を設立、九次米が独占していた 秋田の国有林の払下げを引き継ぐ。 井坂は林産商会能代支店支配人となり、 九次米が経営不振で撤退すると、その資産・負債一切を継承、明治30(1897) 年に能代挽材合資会社を設立、明治40(1907)年には能代挽材、秋田製材、 能代木材を合わせて秋田木材を設立する。
秋田杉は、木目の美しさ、強度、狂いが少ない木材として、現在も高い評価 を得ている。 全国にその名を知られる契機になったのが、井坂直幹が明治30 年代から始めた機械による製材だった。 それまでの木材と違い、規格が揃い、 木目の美しさが一目でわかる板が大量生産され、製品は飛ぶように売れ、全国 に広まった。 天然杉の集散地、能代は「東洋一の木都(もくと)」と称せられ、 木材業を近代産業に育て上げた秋田木材の創業者・井坂直幹は「木都の父」と 呼ばれるようになった。 秋田木材「秋木」は、東京、大阪など国内主要都市 や朝鮮半島にも進出、発電や機械製造などの事業を展開して「秋木王国」を築 いた。
福澤諭吉協会一行は、新緑滴る御指南町の井坂旧宅跡にある井坂公園へ行き、 井坂直幹記念館を見学し、井坂を祀る御指南神社に参った。 井坂公園の奥に、 井坂直幹の胸像がある。 実は、この胸像を昭和44(1969)年に制作したの が、今回の旅行の案内役、畠山茂さんの実の父上、阿部米蔵さん、秋田大学教 授・新制作協会会員の彫刻家だという。 畠山さんは次男で、旧姓は阿部、あ る日、井坂を慕う数人の人が父上のアトリエを訪ね、こう頼んだそうだ。 井 坂直幹翁の胸像を再建(以前のは戦争時に金属供出)したく、別の彫刻家に依 頼していたのだが、高齢で完成できなかった、作りかけの胸像を持参したので、 引き継いでほしい、と。 父上は、作りかけの作品を受け取らず、「私なりに井 坂さんのことを調べてからご返事します」と一行を帰した。 父上は、感動に 値する人物でなければ、その人の彫刻像を手掛けることはなかった。 やがて、 井坂直幹のことを深く納得して、全く新たに制作したのが、現在の胸像だとい う。 数年前、父上の屋外作品を確認調査していた畠山茂さんは、父上とその 作品を通じて、福沢門下の井坂とご自分とに不思議なご縁ができるものだなあ と、感慨を持って胸像を見上げていたそうだ。
(写真は新緑の井坂公園、奥に井坂直幹の胸像が見える)
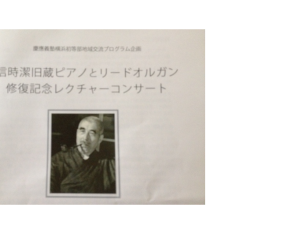



最近のコメント